作家インタビュー 書きたいものがありすぎて
第2回大賞受賞、中脇初枝さん

作家インタビュー 書きたいものがありすぎて
第2回大賞受賞、中脇初枝さん

23年前、第2回坊っちゃん文学賞で最優秀賞を受賞し、作家としてデビューした中脇初枝さん。ここ数年でも、児童虐待をテーマにした連作短編集『きみはいい子』が坪田譲治文学賞を受賞、本屋大賞4位に入賞、さらに児童養護施設で育った女性を主人公にした『わたしをみつけて』が山本周五郎賞にノミネートされるなど、話題作を発表する一方、児童文学など幅広い分野で創作活動を続けています。
坊っちゃん文学賞と出会ったことが全ての始まり
—坊っちゃん文学賞に応募されたのは、今から23年前。まだ高校生だったんですね。
中脇:高校3年生でした。私、高知県中村市(当時)といって、高知県の西の端、四万十川の川沿いの田舎の高校生でしたから、本当に何も分かっていなくて。坊っちゃん文学賞についても全然知らなかったんです。だけど、本はすごく好きだったので、小説を書いてみようかなあ、なんて考えていて。ちょうどその頃、たまたま高知新聞で「坊っちゃん文学賞募集」の小さな記事を見つけたんです。それまでは、そんな文学賞の存在も知らなかったので、その記事を見て、あ、お隣の愛媛の賞なんだなあって。規定が100枚だったので、それくらいだったら書けるかも、と思って書いてみた。とにかく何もわからないまま、締め切り間近で慌てて書いたのを覚えてます。
—書きたいテーマがすでにあったということですか?
中脇:受賞作品(『魚のように』新潮社刊)の最後の方に、詩が出て来ますが、まず、その詩が生まれてきたんです。この詩、いいなあと思って、それを書いたのがきっかけで小説を書こうと思いました。
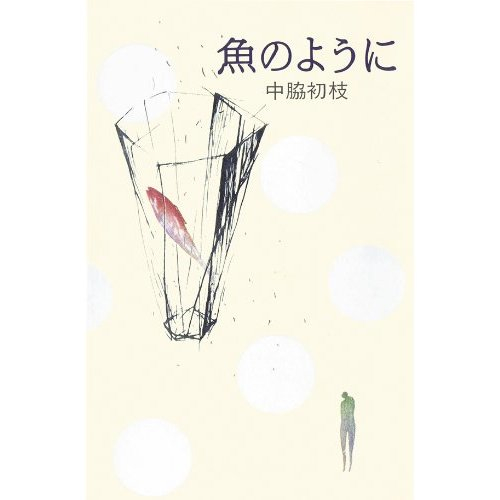
—この受賞作品は、人物の心理描写もさることながら、風景描写も非常に繊細ですが。
中脇:わたし、風景を見るのが大好きで。景色を見て、それを文章にするのが、すごく好きだったんです。坊っちゃん文学賞に応募するまで実際に小説を書いたことはなかったのですが、文章を書くのはすごく好きだったんです。国語が得意で、古典も大好きで。あとは妄想も好きでした(笑)。高校生なんて、世界も狭くて自分の知ってることで勝負するしかないですよね。だから妄想で書きました。今でもそうですけれど。
そうそう、高校時代には一人でエッセイも書いてました。新聞の記事について、原稿用紙2枚くらいの文章で、誰に読ませるわけでもなく一人妄想エッセイ(笑)。江戸時代が好きだったので、その時代の言葉で、一人古文エッセイを書いたりもしてました。ははは。恥ずかしい。
—高校で文芸部に入ったり?
中脇:そういうのはなかったんじゃないかな。高校のときは同じクラスに仲良しの子たちがいて楽しかったですね。彼女たちは勉強がよくできて、読書感想文もとても上手でコンクールに出品されたりするのですけれど、私は妄想ですごくおかしなことを書いちゃったりするから、絶対に選ばれなかったですね。
—子どもの頃から本好きだったんですか。
中脇:両親は本を読まない人だったので、私が小さい頃、家には本棚らしきものがありませんでした。母も仕事で忙しかったので、私、絵本を読んだ経験がなかったんです。物心ついたときには絵本ではなく「本」を読むようになっていました。絵本の体験は乏しかったのですが、本は大好きでした。
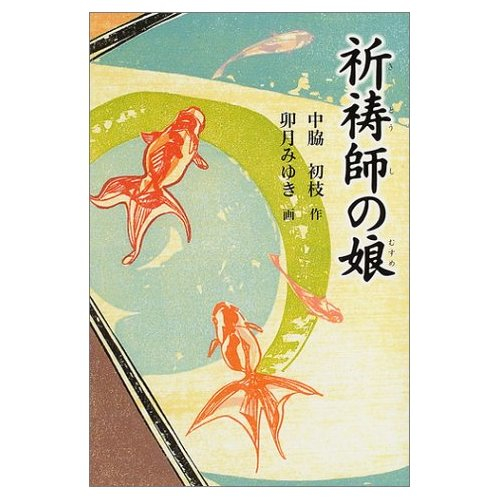
受賞して始まった「物書き」人生
—受賞後、各出版社からオファーが?
中脇:そうですね。いろんな出版社の方からご連絡をいただき、最終的に受賞作品は新潮社さんから出版していただきました。もともと、新潮文庫がすごく好きだったということと、担当の方が女性だったから、なんとなく安心できたということもあったかな。
—高校卒業後、進学されていますが、作家生活に入られたのは大学卒業後ですか?
中脇:いや、作家生活なんて、意識したことはないです。なんとなく地味に書き続けているだけで。柳田国男が好きで民俗学者になりたいとも思っていたので、大学では民俗学を専攻しました。大学時代も小説を書いていましたが、別に「作家になる」と思って書いていたわけでもないですし、ただ書くことが好きで、書きたいことがあるから書き続けてきただけです。
小説を書いていないときも、エッセイや、子ども向けのお話の仕事など、いろいろ書かせていただいてます。エッセイを書くと、とても勉強になりますね。小説は、書いてしまったら、あとは読者の皆さんがご自由に、というところがありますよね。でも、エッセイはほぼ同じことを感じてもらえるよう、わかりやすく誤解のないように短い文章の中で書かないとなりませんから。

—テーマが見つからないとか、書けないといったスランプはありましたか?
中脇:そういうことはあまりないです。常に書きたいものがあります。逆に、書きたいのに書ききれていない、間に合っていないというのがプレッシャー。
どの作品も、最初にイメージが湧いて書き始めるのですが、書いているうちに人物が勝手にどんどん動き出していく感じです。私自身、書きながらラストがわからない時が結構あります。昨年出版した『わたしをみつけて』は、ラストが本当にわかりませんでした。書いていて、(すごい! この人、こんなことをしちゃうんだ、格好いい!)って自分でびっくりしました(笑)。
—虐待してしまう親の苦しみ、子どもの痛み、書いていて辛くはなりませんか?
中脇:とても辛いです。書きながらそれぞれの人物が生きてしまうので、すごく苦しいです。泣きながら書いています。書いた後は、いつも家族に「書いていたでしょ」って見抜かれます。泣きましたっていう顔になっているから。そうすると、子どもたちも母親の作品を読もうという気にはならないみたいで(笑)「お願いだから、もっと楽しいお話を書いて。ファンタジーとか」って頼まれます。

書きたいことがあるから書き続ける
—書きたいと思うテーマに、どのようにして出会うのでしょうか?
中脇:うーん。普通に暮らしている時です……。喫茶店などで他人を観察するのが面白いっていう人がいますが、私には全く理解できません。本当にその人に興味がわいたら、私だったら付いていって話を聞かせてもらいます。
昔から、私は人の話を聞くことが大好きでした。中学校の時、家族が入院し、その隣で寝ていたおばあちゃんにお祭りの話を聞かせてもらったことがあったのですが、つい先日、そのお祭りの場所に行く機会があって、そこに、彼女の話通りのことが書かれた看板が立っていました。何十年もたっていましたが、彼女がここで暮らしていて、ここのお祭りを楽しんでいたことがわかりました。人から聞かせてもらった話を、すごくよく覚えているんです。

—柳田国男のフィールドワークに近い感覚でしょうか。
中脇:私はそっちのタイプですね。今も、日本各地に行って話を聞かせてもらっています。近々奄美にも行ってきます。前に出した『女の子の昔話』の中の『ホーラのマーヤ』という昔話がきっかけで、つながりができたんです。やっぱり、自分が好きなことを一生懸命やっているとつながっていくんですね。
福島にもいつか行きたいのです。福島には『ゆきおんな』の素晴らしい語り手さんがいて、そのお話を絵本『ゆきおんな』で再話しました。昔話は大学時代からずっと追い続けていますから、故郷がたくさんできました。

—自分の創作活動の中で、大切にしている部分は?
中脇:どの作品も自分のために書いているのですけれど、それだけではなく、「この子たちのために書きたい」とか「世の中に問うていきたい」といった思いがあります。児童虐待をテーマに小説を書いたのも、当事者が言えないことを言ってあげたいという思いがあるから。特に子どもは言葉にして表現できない子が多いですから、このテーマはいつまでも続けたいです。
一方で、デビュー作『魚のように』は、本当に自分の好きなことを好きなように書いた作品です。そして今、『小説新潮』で連載中の『川にすむ神は水にくすぐられてわらう』も、あの頃から23年ぶりに、書きたいものを書きたいように自由に書いています。あのときの感覚に戻った感じです。
—「作家」を目指す人たちに、伝えたいことは?
中脇:わたしは、「作家」という肩書きで紹介されることが多いですが、自分では作家だと思ったことはあまりないのです。文章を書くことが好きで、書きたいことがある人は、ぜひいっぱい書いてください。「作家になりたい」というのは何か違うような気がするのですが、「文章を書きたい」というのであれば、好きなことはいっぱいやったらいいと思います。
私も、まだまだ書きたいことがたくさんあります。「ファンタジー」もこれからの宿題の一つ。子どもたちも楽しみにしてますから。
■中脇初枝 プロフィール (なかわき・はつえ) 作家。1974年生まれ。高知県中村市(現・四万十市)育ち。高校在学中に『魚のように』で第2回坊っちゃん文学賞を受賞。その後も小説や絵本など、作品を発表し続ける。現在は『小説新潮』にて『川にすむ神は水にくすぐられてわらう』、web福音館にて『ちゃあちゃんの昔話』(高知県幡多地方の昔話)を連載中。