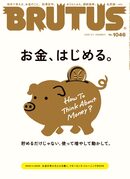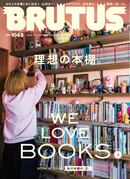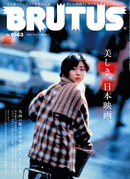みやげもんコレクション 173 馬ッコツナギ
岩手県/花巻市
文 / 川端正吾

2頭仲良く並んで神様をお迎えする大迫の藁馬。
岩手県の農村には藁で編んだ馬を、田の水の取り口や井戸、氏神、道の分岐点などにお供えする風習が数多くあります。村ごとにその方法や馬の形は様々。今回ご紹介するのは花巻市大迫町に伝わる「馬ッコツナギ」。岩手の藁馬の古くからの習わしを最もよく残しているといわれています。馬が備えられるのは6月15日の早朝。うるち米を砕いて練ったシトギを葛の葉でくるんだものを藁馬の口にくわえさせ、これを抱えて駒形神社へ向かうのです。馬は雄雌一対になっており、綱で繋いであります。こうした綱で繋がれた馬は他の地域では、綱を張って馬を吊り下げることが多いですが、ここではそうはしません。2頭を並べて置き、両脇の地面に小枝を突き立て、綱の両端はそこに結びます。この2頭のうち1頭は、神様の乗り物となってお出ましになり、もう1頭は食糧を運ぶ馬として、田畑の見回りや遠国で行われる神様の集まりへのお伴役になると考えられています。この神様は天王様、つまり牛頭天王であると伝えられる地域が多いことから、天王社の縁日である6月15日に藁馬の奉納が行われることが多いです。


掲載:BRUTUS#768 (2013年12月15日号)
値段・問い合わせ先などは、発売当時のものです。