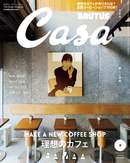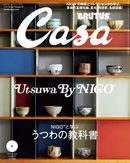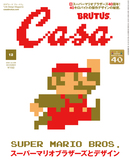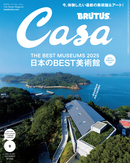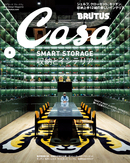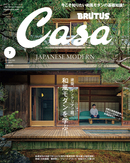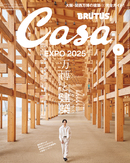うつわ特集で買ったもの、欲しかったもの Editor’s Voice No.242
Editor’s Voice
うつわ特集で買ったもの、欲しかったもの
料理家に人気のうつわ作家はやっぱり料理上手でした。
最初にうつわ特集をしてから12年。取材先や作家の個展でうつわを買いまくり、今や家の中に10人家族でも足りるくらいの量がある私。
もう十分だろう、と思っていたのに、作家の自邸に伺って、自作のうつわでごはんを作っていただくと、やっぱりうつわが欲しくなってきた…。
うつわは料理を盛ってこそだということを再確認しました。
巻頭でご紹介している人気作家7人の作品から、欲しかった&買ったものをご紹介します。
彼らの家ごはんレシピとうつわの使い方は本誌をぜひ!
1.二階堂明弘さんの焼き締め赤ボウル

錆びたような風合いと、高台がなく、薄くてシンプルな形がおしゃれなうつわだなー、と思っていたけれど、二階堂さんがルーローハンを盛ると、一気に台湾の屋台のような香りを帯びてきた…? モダンな佇まいなのに、ざくっと盛っても縁が割れてもサマになる懐の大きさに惹かれました。
photo_ Norio Kidera
2.余宮隆さんの輪花四寸皿

澄んだ深い海を思わせる余宮さんの小皿。私物を見せていただき、偶然生まれた釉だまりの美しさに釘付けになってしまった。こんなうつわに、いつか出会いたい。手にいれたら、何をのせようか…塩や餅や、白くてきれいなものがいいかな。塩昆布もいいかも。
photo_ Yoshikazu Shiraki
3.谷口嘉さんの花器

一見、薄くてモダンで端正な谷口さんのガラス。でも近づいて見ると、表面がざらっとしていることに気づく。この硬質なゆらぎは、吹きガラスにコンクリートの型を用いることで生まれたものだそう。またトルソー型の花器は、口スレスレまでたっぷり水を注ぐと、まるで大きなガラスの塊のよう。そんな意外性と色気に、グッと惹きつけられました。
photo_ Norio Kidera
4.杉田明彦さんの漆椀

ゴツっと無骨なうつわやアジアのラフなうつわが好きな私。いつかは漆のうつわを…と思いながら、端正な佇まいに気後れし、決めきれないまま10年が経ってしまいました。が、ついに出会ってしまった、という感じです。杉田さんの漆は至極まっとうなのだけれど、形が少しだけユニークで、色合いもシック。さらに、ご自宅にうかがって料理をいただくと、食卓には漆に合わせて分厚いうつわが並んでいました。聞けば、杉田さんも分厚い陶器のうつわが好きだとのこと。それで即決しました。写真は塗り分けですが、私が買ったのは深い赤。はじめての漆椀、使うのが楽しみです。
photo_ Norio Kidera
5.熊谷幸治さんの土鍋炊き用のうつわ

日本ではたったひとり、独学で土器をつくり続ける作家の熊谷幸治さん。彼のうつわは使い込むほどに革のような風合いになるところがとても素敵で、いくつか持っていました。今まではうつわとしての土器しかつくったことがないようなのですが、縄文時代はそもそも煮炊きにも使われていたのだから、と今度は調理器具としての土器を作ったのだそう。「生の野菜を炊くと、濃厚でみずみずしくて、味わったことのない食感が楽しめます!」と興奮気味に、神楽坂〈さいめ〉の嶋田シェフと野菜を炊いてくれました。写真は嶋田シェフが持ってきてくれた土鍋。右から時計回りに、半年使用、2カ月使用、2-3回使用したもの。右は地もしまっていい風合い。骨董と間違えられたこともあるそうです。
photo_ Futoshi Osako
6.井上尚之さんのスリップ角鉢と呉須釉薬双耳杯

熊本、小代焼きの400年の伝統を引き継ぐ井上尚之さん。近年はスリップウェアなどさまざまな技法も取り込み制作を続けています。「小代焼きが400年も残ったのは土地の食事に合っていたからだと思う。自分がつくるうつわの基準も、我が家の暮らしに合ったもの」と言い切るだけあって、郷土料理がよく映えました。スリップウェアは買えなかったけれど、青菜にも合う深いグリーンに惹かれて、左の呉須釉薬双耳杯を購入しました。
photo_ Yoshikazu Shiraki
7.竹俣勇壱さんのカトラリー

本誌でご紹介したのはステンレスのプレートですが、竹俣さんはカトラリーも素敵です。ギャラリーで手前のスプーンを見つけ、昔アジアで買ったサーバースプーンに似てる! と興奮していたら、その通り。「料理家から、ベトナムのサーバースプーンのより使いやすい形を求められてつくりました」とのこと。アジアとアジア飯が大好きなので本家本元のは家に何本もあるけれど、素材のよさと形の美しさにやられて買ってしまいました。美しいものって罪ですね。
photo_ Norio Kidera